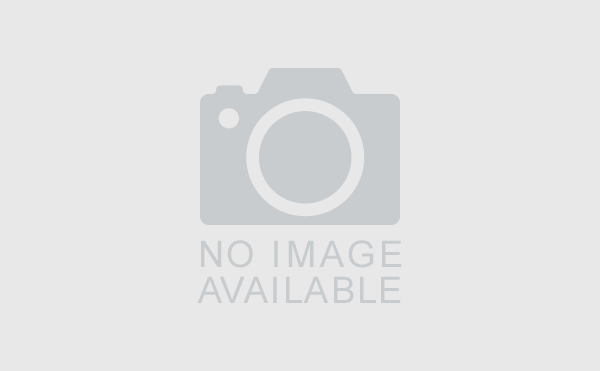振り返りと近況のご報告
ブログをはじめたときに、自己紹介文をつくっていましたが、いろいろと変化がありましたので、これまでを一旦振り返りつつ、近況のご報告ができればと思います。
以下、長文になります。
コンテンツ
仏像を好きになる

私が仏像を好きになったきっかけは、15歳のとき、東大寺法華堂の仏像を拝観し、なかでも不空羂索観音像の圧倒的美しさに心奪われました。
また1300年という途方もない時を過ごしてこられた存在と対面して、同じ時間を共有している奇跡に感動し、仏像がつくられた背景に、仏像が見つめた景色に、興味をもち、日本仏教史の先生がいらっしゃる大学へ入学しました。
大学時代は「将来、文化財や仏像を守る仕事がしたい」と思い、学芸員になることを目指しつつ、好きなことを学べる楽しさを日々感じていました。
地方仏巡りをはじめる
大学時代のある日、仏像好きネットコミュニティのオフ会へ参加しました。
そこで出会った方々に全国各地のおすすめ仏像や推し仏を教えていただいているなかで、
「そういえば地方仏は行った?地元の方がお守りしているんだけど。滋賀県の湖北あたりとかいいよ」
とお勧めしていただきました。

そんなこんなで、井上靖氏『星と祭』の舞台であり、仏像めぐりのスペシャリストたちもおすすめする湖北こと、滋賀県長浜市へ関心をもち、まずは行ってみることに。
湖北の仏像は「〇〇寺」という名でありながら、地元の方々によってお守りされているお堂にいらっしゃいます。
今でこそ慣れたものの、事前に電話予約するシステムも、初めてのことでした。
お参りにいくと地元の方が「ようお越しになりました。どうぞお上がりください」とお声かけくださり、厨子に向かって静かに手を合わせ、戸を開けてくださる。
現れた観音像へ目を向けながら「うちの観音さんは…」と地元の方は語りだされる。
その紡がれる言葉は、あたたかく、仏像とのつながりの深さが感じられました。
仏像へ向ける地元の方のまなざしは家族にむけるような親しみあるもので、仏像もまた、柔らかく穏やかな雰囲気をまとっていました。
ともに同じ村に暮らし、寒い冬も山笑う春もともに過ごしてきた。
今日一日の無事に感謝し、明日も穏やかに過ごせることを祈る。
困った時に、夫婦喧嘩をしたときに、うちの観音さんに相談する。
子どもの健やかな成長を祈り、その子どもが大人になった姿を観音さんはそっと見守る。
そんな日常生活に自然と溶け込んだ、穏やかな祈りの文化がそこにはありました。
そんな地元の方々と仏像がともに暮らす光景が幸せそうに見えました。
そして、純粋にこれからもその光景があり続けてほしいと思いました。
これを機に湖北や滋賀県だけでなく、あちこちで祀られている地域の仏像たちにもお会いしたいと思うようになり、地方仏巡りを始めるようになりました。
地方仏を巡るほど、地域の仏像と人の関わりあいに興味をもち、また過疎化、高齢化など、地域の仏像がおかれている状況の厳しさを知ることになりました。
滋賀県湖北地方へ移住

「特別な力もない、ただの仏像好きの私だけど、何か力になれないのか」
地域の仏像を拝むたびに、そんなもどかしさを抱えながら社会人となり、日々せわしなく働いていたときに、長浜市が「観音の里プロジェクト」という枠で地域おこし協力隊を募集していることを知りました。
「あれこれ考えているよりも、現地へ飛び込んで、できることを模索する方が早いかもしれない」
「国内留学だと思って取り敢えず行ってみよう」
そんな思いで協力隊に応募し、そして長浜市へ移住しました。
地域おこし協力隊にて
協力隊の3年間は、とにかくお堂へ足を運び、地元の方々とお話をしました。
仏像の拝観対応やお堂に関連する地域行事などを担当する世話方と呼ばれる地元の方々、また、それらの役を終えたOBOGや祭りなどの行事に来られる方々に声をかけて、「村の仏さん」との思い出や思い、地域行事や地域でのくらしについてなどを聞かせていただきました。
一方で、執筆やトークイベント、アテンド、広報PRなどをして、自分にできることを試行錯誤しました。
『星と祭』復刊プロジェクトでは、『星と祭』の復刊に合わせて実行委員会メンバーの皆さん、そして出版社の能美舎さんの後押しで自分の本も出版することに。
現場へ足を運び、地元の方と言葉を交わすほどに、
「カウンセラー、相談員のような存在や仏像を守る当事者へのケア、サポートが必要ではないか」
「それをボランティアでするには限界がある」
「仕事にできたら、有限の時間をそこに当てられる」
と感じ、そのようなお役目をいただけるようにがんばろう!と思い、協力隊活動をやりきりました。
仏像を守る方々をサポートする
その思いが形になり、協力隊の任期終了後は、自治体が事務局を務める団体から業務委託を受けて、
・仏像や神像などが安置されているお堂の状況やお守りされている地元の方々の体制などの実態調査
・仏像を守る地元の方々からの相談対応
・交流会や対談イベントの企画・実施
・情報発信
などの仏像を守る方々をサポートする仕事に5年間携わってきました。
※現在、こちらの事業から離れています。
お堂での調査や相談対応では、困っていることや悩んでいることはないか、地元の方々の声に耳を傾け、悩み事を一緒に考えたり、こうだったらいいのにと言い合ったり、何か役にたてば…と情報提供したりしてきました。
「直接的解決に結びつかなくても、いつかそれが何かをはじめたり、考えたりするきっかけの一つになれば」そして、「その年の世話方さんや中心となっている方々が背負うものをほんの少しでも軽くできれば」と思って携わってきました。
また、業務委託事業とは別に、お堂の修復資金を集めるクラウドファンディングの広報サポートというかたちで、伴走支援することがありました。
何よりも、地元の方々がこれまで丁寧に拝観者対応をされたり、展覧会などに協力されたりしてきたこと。
クラファンでも地元の方々自ら一生懸命行動されたこと。
そして、多くの方々がその声に応えてくださったからこその達成だと思っています。
学生時代に「特別な力もない、ただの仏像好きの私だけど、何か力になれないのか」と思っていた私にとって、微力ながらサポートでご一緒できたのは感慨深かったです。
一方で、講演会やイベントで湖北や滋賀県を中心に、祈りの文化や地域の仏像を守ることなどについて話したり、文章にしたりして伝えることを続けてきました。
関わり方を見つめなおす
大学時代の私がみたら「仏像を守る方々をサポートする仕事ができているのだから、それでいいじゃないか!」と思うことでしょう。
しかし、仏像を守る地元の方々に寄り添ってきたからこそ、伴走支援してきたからこそ、いまのままの自分では十分な力になれないと感じています。
そのもどかしさから、「仏像を守る」「地域でつないできた文化をつなぐ」ということに対して、「自分はどのように関われるのか」ということを考えるようになりました
そういった背景から、昨年の夏からファンドレイジングについて勉強を始め、2025年1月に准認定ファンドレイザーの資格を取得しました。
その過程で、ファンドレイジングに関する知識だけでなく、「応援したい」という気持ちに対してどう向き合い、どう行動するかを改めて考えるようになりました。
また、私事ですが、難聴が進行(聴力が低下)し、体調を崩したこと、そのほかに色んなことが重なりまして、今後の自分の働き方を含め、色々と悩むこともありました。
※現在は補聴器を装用してお仕事をしています。
昨年の冬から今年の春にかけて、仕事の量を調整しながら、休み、自分とじっくり向き合う時間としました。
ふりかえってみると、滋賀へ移り住んで、仏像を守り、ともに暮らす方々と向き合い続けて8年が経ちました。
これまで仏像を守る方々と接するなかで、その時々の会話を大事にしてきました。
仏像への思い、先人から伝え聞いた暮らし、そしてその思いをよく耳にしました。
そんなお話を聞けば聞くほど、その土地の人から受け取ったもの、ことを伝えたいと強く思うようになりました。
仏像を守ることと、そのまわりにある人々の営み、文化を伝えることは、ともにあることだと思っています。
今、当たり前だと思っている景色や空間も、記録がなかったら「そんな時代があったの?」「はじめからなかった」と思われてしまうかもしれない。
それはとても恐ろしく、悲しいことで、決して大袈裟な話でもないように思います。
ならばせめて人々の思いや土地の文化を伝えたい。
そして、これからの時代の人たちがあとで遡って知れるように、残したい。
それは長浜市内や滋賀県内に限らず、その土地に息づくものでありながら、埋れてしまっている歴史や文化、それに関わった人々の声にならぬ声に耳を澄ませて、それを言葉にして伝えることができればと思います。
そして、いま
仏像、歴史、文化について、文章を書くこと、話すことといった「伝えること」は、これからも続けたいと思っています。
これまでメインで携わってきた「仏像を守る人々をサポートするお仕事」から少し距離をおいて、文化系の仕事のお手伝いをしています。
これまでは現場に関わり続けながら考えてきましたが、いったん立ち止まり、少し異なるかたちで地域や文化に向き合ってみようと思います。
自分の体とぼちぼちに付き合いながら、続けたい「伝えること」を細々と続けつつ、別の働き方で新しい学び、経験を重ねたいと思います。
だから仏像を守ることに関わらないということではなく、ささやかではありますが「伝えること」のなかで関わりながら、模索したいと思っています。
どうぞ、これからもあたたかく見守っていただけたら幸いです。